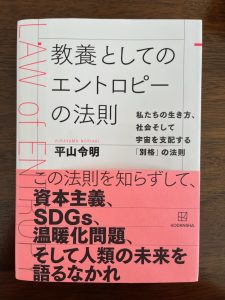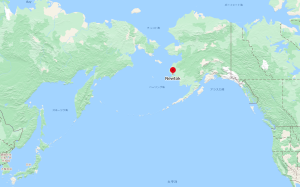総おひとり様社会
2020年の国勢調査では、単独世帯が一般世帯の38%を占めたとのこと。
東京都に限ると50%を超えている。
夫婦と子供2人という旧モデル世帯は1割を切る。
3世代同居は4.1%。
※日本経済新聞より
1人は気ままでいい。
私は50年間、いつも誰かと一緒に暮らしていたし、ずっと仕事をしていたから、1人でいられる時間などほとんどなかった。
子育てが終わり、1人で過ごす時間が断然増えた。
時々家族と過ごす時間は大切だし愛おしいと思うが、ひとり時間の快適さは捨てがたい。
長年1人暮らしを続けている人たちが、「他人と一緒に暮らすなんて無理![]() 」と口を揃えるのも理解できる。
」と口を揃えるのも理解できる。
適度な繋がりを感じながらも自由でいたいと思ってしまう。
まぁ、要するに、私はわがままな人間だと思う。
社会(社会って誰?)が個人主義を目指し、民意がそれを許容した。
個人の権利主張が強くなった。
これは欧米社会を模倣したからに他ならないが、表面的な制度だけを輸入し、魂が伴っていないからおかしなことになっている。
もともと日本人は控えめで謙虚で、空気を読み、周囲に合わせることが得意だし、善しとする文化だ。
個人の権利より、公の利益を優先してきた国だ。
この同調圧力は、コロナ禍で露になった出来事である。ある意味恐ろしかった。
私も若いころはアメリカ留学なんてしたものだから、そういう日本の堅苦しい習慣を毛嫌いしたものだ。
しかし、長く生きて、いろいろ経験し学んでいくうちに、日本の歴史、文化、精神性というものの成り立ちを知ると、張りぼてのような制度設計には無理があると思う。
日本人らしさという大和魂を無視しては上手くいかない。
80代の知人が現役で働いていた1980年代頃、彼女の会社では連休取得は4日間が限界だったという。
1週間も取れる雰囲気ではなかったし、皆もそんなものだと思っていたという。
4日間の短い海外旅行にたくさんのOLさん達が参加していたそうだ。2泊4日の旅??
私が研修医として働いていた90年代も、夏休みは1週間もなかったし、有休休暇という概念すらなかった。これは医師という属性だったからかもしれない。
真面目にコツコツ働くことが美徳であり、自分の出来ることが増えると純粋に嬉しかった。
休みもなく働くことがカッコ良かったから、睡眠時間を削って仕事した。
それでも夢と未来があったから苦にならなかった。
20年以上経った今、働き方は大きく変わった。
有休や育休取得を推奨し、残業を減らすことが良いとされる空気を感じる。
労働時間は1996年に1915時間、2021年は1651時間へ減少。
ところが日本国民1人あたりの労働生産性は1996年からほぼ横ばいとのこと。
米国は2.5倍、英国は2倍に増加しているのと比べると、停滞感を実感する。
労働時間は減ったけれど、仕事の成果も減ってしまったということ。
働き方改革は何か間違っているのだと思う。
真面目にコツコツ、人のためになる仕事をしている人が報われる社会であって欲しい。
さて、権利主張の激しい個人主義社会を模倣した日本。
核家族化が進み、とうとうひとり暮らしがスタンダードになった社会。
ひとり暮らしの高齢者をどうやって支えていくかが大きな課題である。
自由には責任と義務が伴うという原理原則を忘れてはならない。
人はひとりで生きていくことなどできず、家庭や学校、会社という社会の枠組みの中でたくさんの人たちの助けを借りている。
謙虚で驕らず、感謝の気持ちを忘れない。
そして「忠恕」の心で、志欲を持って生きていたい。